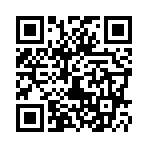2017年04月06日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になると その11
先日、横西アウォーズを中心に1年間の活動や試合の模様を収録したDVDを見ていると、
4月から高校3年になる長男が一言
「もっと早く、このチームを作ってくれればよかったのに…」
小学校からの長男のサッカー人生を
そばで見守ってきた私にとって、
その一言にたくさんの重みを感じました。
それでもあえて、
「どうしてそう思うの?」と尋ねると
「だって、みんな、すごく楽しそうにサッカーしてるもんな。
本当にいいチームだと思うよ」
嬉しい一言でした。
同時に、息子の状況に思いを馳せました。
きっと、たくさんのサッカー少年・青年が
息子と同じような思いをして、
たくさんの保護者が
私と同じような思いをしているのだろうと想像します。
実は、このシリーズに書きたいことはまだまだあるのですが、
4月に入り、私が引退した横瀬西SFCも新体制、
新メンバーで新年度に突入しましたので、
一旦、執筆をお休みします。
今、伝えたいのは、子供たちの今、この瞬間を逃さず、
見て、できていることを認めて、
できていないことを見つけたならば、
できない理由を一緒に探してあげてほしいということです。
子供たちはいつも頑張っています。
お父さん、お母さん、チームの仲間、
監督、コーチに認められたくて、ほめられたくて!!
それでもできないときは、ちゃんとできない理由があるのです。
だから、大丈夫!
どんなにほかの子と比べてしまうと、
ふがいない息子や娘に思えても、
彼らや彼女たちが、
その理由を見破り、改善する方法を
伝えてくれる指導者や大人に出会えれば、
大きくなって、自分で気づいていけば、
きっと成長していけるのです!
人の性格が十人十色であるように、
成長の速度や過程、できるようになることの順番、
体の使いかた、呼吸の仕方、みんなみんな十人十色です。
あなたの息子さんや娘さんを信じてあげてください!
サッカーを楽しんでいることを単純に喜んであげてください。
仲間と仲良くできていること、
仲間と意見を交わしあえることを
一緒に喜んであげてください。
15分間、20分間、
ピッチで戦えていることをほめてあげてください。
どんなところが素敵だったのか、
どんなところが良くなればもっと輝けるのか、
見つけて、伝えてあげてください。
そうすることで、きっと子供たちは、
自分を信じる“自信”という人生で重要な礎、
友とも呼べる“見方”を手に入れることができます。
そのために、まずは、大人が子供たちを信じてあげて、
ピッチのそとから声援を送ってあげてください。
そして最後に、コーチの皆さん、
どうか、できない理由を見抜けて、改善できるように
よくよく子供たちを観察して、
そして、勉強をともに続けましょう!
ボランティアだから、
忙しい仕事の合間にやってるんだから、
自分の家族を犠牲にしてでもやってるんだから
という言い訳は、
大人同士の協力で言わないで済むようにしていきましょう!
そして、子供たちに教えてもらいましょう。
できない理由は子供たちの中に確かに存在します!
そして、その理由をわかった上で、
子供たちに問いかけましょう。
何時までも「なぜできないんだ!何回も言ってるだろ?」
といってしまうのは、
あなた自身が「わかりません」「私にはお手上げです」
といっているのと同じであることに気づいてください。
指導者を名乗る以上、
一人一人のサッカー人生が、
輝くための全力のサポートを
共に目指していきましょう!
サッカーを知らない女(ヤツ)なりの、
失敗と反省から出た
心の声でした。ありがとうございました。
2017年03月31日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの指導者になると その10
横瀬西SFC3年目になると、
低学年の新メンバーにとって私は、
はじめから“監督”でした。
それまでの同級生のお母さんからは、徐々に卒業できました。
登下校中に私を見かけると
「あっ!かんとく~!!あのひと、俺たちのチームの監督なんで~」
と、可愛い声が話しかけてくれるようになりました。
この頃からやっと、私自身が考える、
目の前の子供たちに即した(つもりの)練習メニューができるようになりました。
正直それまでは、
「挨拶できるようにしてほしい」
「時間を守れるようにしてほし」
というしつけというか、
団体行動のいろは的なことを求められました。
チームでもやらないことはないけれど、
挨拶や時間のことは家庭でやってよ!と、
最初はぶつくさ文句もいいましたが、
サッカーの指導者が執筆している本を何冊か読んでいく中で、
考えが変わりました。
見つけた良い方法は、
①できた子を率先して褒めること
例えば、グラウンド整備や用具の片づけになると、
どうしてもさぼろうとする子がいます。
そんな子は、目立ちます。
ほかの子たちもさぼる子たちを見つけて
「○○君、せんので~」と、報告に来てくれます。
けれど、さぼる子にフォーカスして怒鳴っても、
子供たちの間にちょっとした隔たりができるだけで、
チームの活性化にはつながりません。
そこで、一番に取り組んでくれた子や、
いつも取り組んでくれる子、
丁寧な仕事をしてくれる子たちを、
理由もつけて誉めることにしました。
「はるあき、いつも気が付いて、マーカー集めてくれてありがとう!」
といった具合です。
そうすると、低学年では、競うように片付けがはかどりました。
高学年でも、相手を非難する言葉は減り、
自然にゆるやかな役割分担ができてきました。
もう一つは、試合や練習試合で
②良く挨拶ができるチームや礼儀正しいチームを紹介して褒める
ことを始めました。
特に、審判への感謝の心を持ってほしかったので、
審判に対する態度の良かった対戦チームを、試合の直後にほめて、
彼らが審判にどんな態度や挨拶をしているのかを具体的に紹介しました。
するとある時点から、キャプテンが、
試合後必ず審判団に挨拶をしてくれるようになりました。
(これを毎回やると、次の試合の開始を遅らせたり、選手の渋滞を招く
ようで、あまり良い顔をされない時もありますが)
まだまだ、伝統あるチームには追い付いていませんが、
「挨拶しようね」「挨拶しなさい」「挨拶は!?」という
声掛けだけでは進まなかったしつけ(?)が、
ある程度の成果を上げたと思っています。
①と②は、練習のクオリティを上げる際にもとても有効に使えました。
もちろん、今できていないことが何かをはっきりさせるための
コーチングも重要ですが、
上級生が少なく、できて間もないチームにとって
目指してほしい姿や何が目指すべきものなのか、
そのいくつかを
日常の中で具体的に知らせることは、とても大事なことでした。
そして、自分たちの話し合いの中で、
目指したい姿や目指すべき何かを具体化して
練習に取り組めるチームになっていってほしいと
願いました。
なので、横瀬西SFCは、割とたくさんのミーティングを
行ってきたと思います。
試合のビデオを見ながらのミーティング。
練習試合や試合の中でのミーティング。
雨の日の練習の代わりにミーティング。
そんな中で、子供たちが感じていること、考えていることを
教えてもらえることが、とてつもなく貴重で、楽しい時間でした。
サッカー分析の奥深さはさておき、
サッカーの初心者でも、試合に出ていない子でも
全員が意見を言えました。
子供たちは、どんな瞬間でも、ちゃんと考えているんだと
当たり前のことを見逃してはならない気持ちで
取り組んできたのです。
2017年03月29日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になると その9
9番君の話を書きます。
横瀬西SFCのエースナンバーは、
子供たちの間で、10番ではなくて9番なのだそうです。
創立2年目で、その9番を背負っていた選手のことを少し書かせてもらいます。
彼は、少年団とクラブチームでのサッカーを経験して
約1年のブランクを空けて5年生で横西に入部してきました。
足が速くてキック力もあり、何より、
一緒に入ってきた同学年の仲間のあこがれの的でした。
対外試合で彼のプレーを見てくれたほかのチームのコーチたちから
口をそろえて、「大切に育ててあげてくださいね」と、言われました。
一人抜きんでていたので、
チーム内のほかのメンバーの動きとかみ合わず、
思い通りにプレーできない葛藤と
長い間戦っていたと思います。
もう一つ、彼が戦っていたのは、どうにもならない現実だったと感じています。
本当は、横西の前に所属していたクラブチームで、
レベルの高いサッカーを続けたかったのだと思います。
彼は入部当初、よくそのクラブチームのユニフォームを着て練習に来ました。
それしかなかったのかもしれませんが、近くで見ていた私には、
それだけではない思いが伝わってきていました。
卒業前、私は元いたクラブチームへの入団を勧めてみましたが、
「今更、いいです」と、言われたことを覚えています。
そして、別のクラブチームに同期の横西メンバーと入団。
トップチームのメンバーとして1年生から活躍していると聞いていました。
ところが、彼が中学2年生になるころに、
そのメンバー全員がチームを離れたことを知りました。
とても驚きましたが、
よく聞くと、9番君は小学校のころに辞めたクラブチームへの
入団テストにチャレンジしたとのことでした。
それも、控え選手からやり直すことを自分で決めて!
その話を聞いた数日後、彼のお母さんに偶然会いました。
「〇〇君、自分に素直になれてよかったね!応援していますね!」
と伝えると、
「親の覚悟が足りなかったわ。頑張ってるっていうから、
親もできることをやらんとな」
そう、話してくれました。
横瀬西での時間も、彼にとっては無駄ではなかったのだと思い
嬉しい気持ちでいっぱいになりました。
そして、小学校時代勧めても
「いや~、そういうの僕はいいです」と、
遠慮(?)していたトレセン選考にも合格し、
チームでもレギュラーとして活躍しているようです。
横西の最初の2年は、サッカーを続けたいのに、
また、何かのスポーツをしたいのに、
本人の気持ちとは少し違った理由で
所属チームジプシーになっていた
子供たちの受け皿的な存在でもありました。
2017年03月28日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になったら その8
サッカーでは小学校の高学年をゴールデンエイジと呼ぶ。
けれどもそれは平均から上の発育発達を遂げている場合に
所属させて良いカテゴリーの呼び名だと思う。
回りくどいか。
つまり、子供の発育発達は、個々に違う。
ましてやどこから成長していくのかは、遺伝的要素も含めて、
千差万別だ。
骨格は大きく成長していても、内臓の成長が追いついていない子だっている。
神経系の反応が優位に発達している子もいれば、
理屈や言葉の理解とともに動きのイメージやボディーイメージが
膨らむ子供だっているのだ。
もちろん、そんなことはわかった上での
“ゴールデンエイジ”という呼称なのだろうけれど、
実際の指導現場で、このことを深く理解しながら
個別に対応した指導が的確になされているか、
いや、的確に行える環境にあるかどうかは、疑問だと思う。
もう一つ、試合で培われる感覚は、どのカテゴリーでも重要な要素だ。
今行われているW杯日本代表の先発メンバーを巡る談話でも、
各所属チームでの試合出場数の少ない選手への不安が取りざたされている。
強いチームに所属するメリットもあるが、
その強いチームで試合に出場する機会がほとんどない環境の
デメリットは計り知れない。
この二つは、フィジカルコンディショナーとしての視点でもあるし、
サッカー少年を息子に持つ母としての視点でもある。
長男が育つ過程で、この二つを身をもって経験してきたからだ。
長男が所属していたクラブチームに抗議しようと書いているわけではない。
サッカーチームという“子ども”を
たくさんの方の支援の中で0から生み育ててきた私なので、
チーム自体も育つ流れ=歴史の中で、いろいろな考え方や
局面に出くわすことを、少しは知っているから。
ただ、現実、長男は途中から実践の場でサッカーができる機会が
激減していった。その背景には、様々な要素があるけれど、
やはり、勝利を目指すチームであればあるほど、
個の行き詰まりや成長にかけられる時間は少なくなる。
横瀬西SFCは、だからこそ、
少人数、その年に入ってくれた人数で戦うチームで良いと考えた。
6年生が0人の年もあったし、今年も6年生は3人。
新3年生も0人のままだ。
平成28年度は4年生も5年生もたくさんの試合を経験できた。
コーチが6名もいたので、
低学年のカテゴリーも
運動が少し苦手な子たち、
学校内で教育支援を受けている子も
試合に出場できた。
そして、低学年は、
たくさん失敗した。
たくさん負けた。
悔しい思いもした。
後半になって得点できるようになったら、みんなで喜んだ。
失敗や負けに慣れて、やる気をなくすのはどうかと思うけれど、
横西の子供たちは、
失敗や負けを受け入れて、それでも
いつでも「勝てるチーム」を目指している。
失敗することを恐れさせていては、
子供たちの中から工夫は出てこない。
試合中に土いじりを始めてしまうのには驚いたけど、
今は、そんな子は当然いなくなった。
指導者の我慢が肝心だと思う。
そして、横瀬西の子供たちはどの年代でも
試合と試合の間で遊ぶことができる✨
「サッカーの試合も見ないで、やる気があるのか!」
と思う方々のご意見ももっともだと思うけれど、
私は、“ゴールデンエイジまで遊べる選手”を育てたかった!
なぜかといえば、遊べば、体を様々に使うから。
低学年からサッカーをすればするほど、
体の中で使われすぎる筋肉と、使われない筋肉が出てきて、
動作習慣に偏りができるから。
遊びはたいてい、脳が喜びながらやるものなので、
夢中になったとしても、いろんなアイディアに満ち満ちている。
結果、多くのパーツを使い、ボディーイメージを広げていく。
まあ、お察しの通りに、遊びからの切り替えができなくて、
2試合目になるとふがいない戦いぶりで、叱られることもあった。
けれど、それも、経験じゃないですか!
大きな声で怒鳴って整列させて、その場の結果を
大人の思った方向にしたとしても、
きっと、また繰り返すよね。
そのパブロフの条件反射的な大きな声がなければ。
子供たちは、少しずつではあるけれども、
変わってきた。
嬉しいことに、対戦相手のチームのことすぐ仲良くなれたし、
対戦相手の子たちのプレーを称賛したり、
目標にしたり、できるようになってきたんだ。
つまり、遊びながらも周辺視野では、ほかの選手の動きを観察し、
それをまねるーとぃう脳にとても良い学びをしていたのだと思う。
それって、成長した証拠ですよね♡
サッカー協会が掲げるゴールデンエイジに異論はない。
そんな恐れ多いこと、考えてもいない。
ただ、そこを目標に、またそこでは見えづらい現実に即した
“ゴールデンエイジ”の育て方や過ごし方があってもいいのではないかと思う。
横瀬西におけるこの4年間のゴールデンエイジは、
ごくごく底辺(悪い意味ではなく大事な大事な土台だと思う)の
最初の一歩を踏むしかないチームにおける、
キラキラした成長過程だったと自信をもって言える!!
2017年03月26日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になると その7
サッカーを知らない私を信頼したから21人が集まったわけではなかった。
だから、信頼につながるものが何になるのか、
正直わかっていなかった。
横瀬西SFCの話に戻そう。
横瀬西SFCは、設立当初に指導者に指導料を発生することにした。
それは、指導者の交通費であり、
指導者としてのスキルアップのためのセミナー代だったり、
保護者会に図ることなく必要な道具を買うためのお金だったりした。
監督である私がもらわないと、ほかの指導者にも出しづらいので、
私はサッカーを知らないにもかかわらず、もらうことにした。
当初、コーンや、作戦ボードなど、いくつかの道具をそのお金で買った。
三年目には、指導者資格を取りに行くお金もチームで出した。
チームのために毎回頑張ってくださっている審判の更新料も
チームで負担するように話しあいもした。
このことが、ほかのチームの指導者の間に物議をかもしたそうだ。
チーム内の保護者達が、外部のいろいろな立場の方々に相談したからだった。
皆、初めてのことだから仕方がないよね。
でも、結局、心底納得してもらっていなかったようで、
チーム内の人間関係に波乱を起こす材料となってしまったようだ。
“そうだ”とか“ようだ”と書いたのはなぜかというと、
私に直接伝わってくることはなかったから。
フェイスブックで「サッカーを知らない女~」を書き始めた最初の文で書いたけど
スポーツ、運動指導者はボランティア精神を期待される。
そのこと自体を悪いとは思っていない。
けれど、いくばくかでもお金をいただくことで、
そこに責任感や公平性、勉学心、向上心、
そういったものにつなげてほしいと思っていた。
もらわないことの美学があるのであれば、
もらうことの美学もあるのだと思う。
新聞記者時代に、豪日スポーツ教育協会と共同して、
オーストラリアのスポーツ施策「オージースポーツ」を
紹介するシンポジウムを大分で開催した。
オーストラリア在日大使さんも来県してくださる、
大規模なシンポジウムになった。
なぜ、これを開催したかといえば、
新聞記者として、
2002年のワールドカップに向けて、ドーム施設が建設中で
そのドームと周辺施設の運営やポストワールドカップの
良好な運営方法やコストパフォーマンスの参考になる事例を紹介したかった
というのが一つ。
もう一つは、
オージースポーツにおける指導者の統一された養成方法、
派遣方法、国や地域からの指導に対する対価の補助制度などを
紹介したかったからだ。
海外の事例が無条件に良いと思っているわけではなく、
日本の良さももちろん感じているが、
どこの地域でも、指導者が国の定めている基準の養成を受けていて、
共通の基準となるプログラムも存在する。
そんなオーストラリアのボランティア指導者が、国や地域から補助金で
活動できているというシステムは、
活動に参加する人たちのお財布にも優しく、
何より、安全と安心につながるように受け止めた。
サッカーの指導者資格をとることに決めた理由の一つには、
サッカー協会の指導者制度がほかの競技よりも数段、
選手たちにとってよい方向に整備、整理されているからでもあった。
指導者資格を持っていないからダメなコーチだとか
持っているから素晴らしいコーチだとか、
そんな短絡的なことを考えていたわけでは決してない。
でも、チームの皆さんには、
うまく伝わっていなかった“ようだ”。( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
2017年03月26日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になったら その6
「先生、すみません、海外の事情が分かっても、
今の現状を変えようとする人がいなければ、
何時までも変わらないと思います」
大学を卒業して雑誌社で編集記者として働いていた。
スポーツ施設のハードとソフトを紹介する月刊紙で、
取材対象の多くはゼネコンやスポーツ関連の団体、
文部科学省が主催するシンポジウムやフォーラム、
国交省などに出向くこともあった。
連載記事は多彩で、
ドイツの進んだスポーツ施設やスポーツ環境を紹介するコーナーや
トップアスリートへのインタビュー記事、
スポーツを題材とした映画を紹介する記事などを掲載。
日本体育施設協会の機関誌的な雑誌だった。
大学の恩師が紹介してくれた出版社だったから、
恩師の連載記事も掲載されていた。
記事タイトルは「海外スポーツ事情」。
アメリカを中心に、カナダ、ヨーロッパ、オセアニア、
アジア、たくさんの国々のスポーツ環境や
スポーツのとらえ方、
文化としてのスポーツの現状をまとめたものだった。
もちろん、大学の授業でも同じ内容を教えていただいた。
聞けば聞くほど、知れば知るほど、心が躍る授業だった。
私のスポーツのとらえ方は、そんな環境の中で飛躍的に
変化していった。
それなのに、生意気にも、その恩師に向かって私は、
意見してしまったのだ。
恩師のご自宅の近くを散歩しながら、
「海外のことを紹介したって、
国家レベルのシンポジウムやフォーラムで
立派な議論をしたって、
何時まで経っても日本のスポーツの現状は
ちっとも変わらないじゃないですか?」
心臓はバクバク高鳴っていた。
その答えを言ってもらった記憶もないくらいに。
25歳ごろの出来事だったと思う。
恩師はその後、来世の使命に向かって旅立っていった。
ぼんやりと、自分が放った言葉の“ことてん”
事と顛末を、自分でやってみなくちゃなーそう思うようになった。
鬼ごっこをしたい子供たちを集めた
多種目型のタグラグビーチームを創った。
サッカーを自分たちの学校でやりたい子が21人集まった。
新しいコンセプトのチームを創りたかった。
先生、ごめんなさい。
スポーツの取り組み方、スポーツのとらえ方を変える、
思った以上に、簡単なことではありませんでした。
2017年03月23日
サッカーを知らないヤツ(女)がサッカーの監督になったら その5
思いもよらないスタート
どうにかこうにか、爪の先がひっかかり、
日本サッカー協会認定C級ライセンスを取得した。
それから約半年後、
チームを率いる監督になるなんて、想像すら及ばなかった。
だから、地域の子供会の集まりで、
「ゆりさん、資格取ったんだったら、学校にチーム作ってよ!」
とお母さんたちに持ちかけられたとき、
「いいよ」と答えたものの、
それは、そんな子供たち(5人くらい)と、
まずはボールを蹴る
グラウンドを走りまわる
程度のことから始めてみようーくらいの気持ちだった。
そんな、小さなスタートを想像していた私。
そもそも、それがその後のしんどい状況を招いた理由だったように
今は思う。
このことは、チームを立ち上げてからずっと
少年・少女サッカーの今後の行方に避けられない課題だと思うので
特筆しておくが、
少子化の中、サッカーチームが新たに一つ誕生することは、
受け取る人によって、様々な意味を持つのだということを
痛烈に感じる出来事が次々と起きた。
まず最初に、私の名前と息子が所属するサッカーチームのこと、
チームで支払われる指導料(これはその当時は不確定)
初日の練習風景などの情報が、
あるチームの保護者全員が受け取れる連絡網で流された。
自分のことだけならまだしも、息子のことに触れられたこと、
こっそり、練習を見てその様子を勝手な解釈で書かれたことに関して
かなりの憤りを覚えて、抗議した。
そののち、クラブチームとして立ち上げたのか、
少年団として立ち上げたのかという質問を
たくさんの指導者から、何度も受けることになった。
当時、横瀬西小学校のグラウンドを拠点とし、
横瀬西を名乗るサッカーチームは存在しなかった。
一方で、少年団やクラブチームの数チームに所属した末、
サッカーは大好きなのに
サッカーを続けることができなくなっていた数人の子供たちがいた。
どうしてそうなったかはさておき(個人の考えなので触れたくない)、
その子たちが自分の学校でサッカーができたら嬉しいー
というのが、そのお母さん方からの要望だった。
ほかにも仲間がいるかもしれないー
各学年1クラスの小規模小学校。伝統ある野球部もある。
仲間といっても、そんなにたくさんにはならないだろうと思ったのだけれど、
募集をかけてみると、なんと21人の応募があった。
「え?みんなサッカーしたかったの!?」
無計画すぎるといえば、その通りだった。
もちろん、サッカーチームを立ち上げるのなら
(5人くらいを想像して)やりたいこともあった。
そして、フィジカルコンディショナーとしての私にやれることもあった。
けれど、21人という人数のおかげで、
“試合に出られるチーム”を作らなければならなくなった。
監督も必要になった。
けれども、クラブチームにする?少年団にする?
「ゆりさん、やってよ」と言ってくれた保護者も含めて、
そんなことは深く考えていなかったのだ。
クラブチームは、
子供をお金儲けの方法に使っているチーム
少年団から、大切に育てた選手を引き抜いていくチーム
という、考えを持つ指導者もいて、
「横瀬西はどっちなんだ?」という意味も込められた質問だということを
後々、知っていくことになった。
監督を引退した今、もし同じ質問をしてもらえるのならば、
私ははっきりとこう答える。
「横瀬西は、横瀬西スポーツ&サッカーという新しいスタイルのチームです」
2017年03月21日
サッカーを知らない女(ヤツ)がサッカーの監督になったら
大分県では、6日間に及ぶカリキュラムを
土曜日、日曜日及び祝日に3週にわたって通い受講する方法と
5日間にコンパクトに詰め込んで合宿形式で受講する方法とがある。
私は、3人の息子の行事などを考えて、
合宿形式で集中してサッカー漬けになることを選んだ。
その時の年齢が45歳。まだ、体調は不安定だったけれども
それ以上時期を遅らせると、体力的に厳しくなると考えて」、
強行することにした。
講習会が始まって、2つの意味で戸惑った。
一つ目は、県外(熊本や福岡)からの受講者が多く、
実技のレベルが想像以上に高かったこと。
メインインストラクターの人気が高く、彼女から学びたい!という指導者が
数ある講習会の中で、わざわざ選んで参加していた
(私自身も同じ思いだったけれど)。
当然、座学の際の意見交換も活発だった。
2つ目は、大分ではまだ珍しい女性指導者の受講に
スタッフの皆さんが、かなり期待をかけてくださっていたことだった。
出来が悪すぎる受講生で、心苦しいばかりだった。
今も、その時の申し訳ない気持ちはリアルに蘇る。
朝6時から講義が始まり、夕食後9時過ぎまで、実技と講義が続く日もあった。
規定の講習後は、筆記テストに向けた勉強という日々。
台風も接近していたせいで、豪雨の中での実技も続き、
疲労は一気にたまっていった。
そして、あろうことか、1日目のキーパー実技ですでに負傷。
これは後で分かったことだけれど肋軟骨にヒビが入っていた。
体力的に追い込まれるのは覚悟のうえだったけれど、
心の方も思いもよらない方向に追い込まれていた。
若い受講者の中からチラホラ、
「なぜ、サッカーを知らないおばちゃんが受講に来ているんだ?」
「実技で本気でプレーしてもいいんですね?」
などの疑問や質問が出始めた。
それらは、ごく当たり前の反応だったから、ちっとも落ち込まなかったのだけれど
期待をかけてくださっていたスタッフの皆さんを
実技で、ことごとく裏切っていることを肌で感じて
“穴を掘って、入りたい”気持ちでいっぱいだったのだ。
そして、申し訳なさに耐えられなくなった私は
ついに「今回の受講は間違っていました。諦めます」ー
雷も鳴るどしゃ降りの雨の中、インストラクターに申しでた。
メインインストラクターの利光ちはるコーチのおかげなのだ。
最後まで、受講をつづけられたのは。
「いいわけだと思っているのなら、言わないほうがいいじゃないの?」
と助言されて愕然とした。
講義を受ける中で、自分が持っていた疑問に対する疑問も沸いてきた。
かっこ悪い自分と向き合うことも年齢的に?
辛かったのかもしれない。
「思いがあったんでしょう?その思いはもういいんですか?」
当時の通りではないかもしれないけれど、
そう、言葉を返された。
「やれることを、自分からやればいいんじゃないの?」
そうだ!私は、まず、自分を克服しなくちゃいけない!!
阿保かと思われるかもしれない。
陸上競技の指導者資格や、
例えば、アスレチックトレーナーなどの資格にチャレンジすれば、
こんなにいろんな人に迷惑をかけなくて済んだかもしれない。
でも、そうじゃない!物事は繋がっている。
サッカーC級ライセンス受講は、
“私が何者であるか”
“何をどう考えているのか”
“何を伝えようとしているのか”をはっきりさせることが、
どんな立場でも大事なことだと、
思い出すことができた、貴重な、貴重な時間だった。
2016年11月24日
勝つ心
ということが、ひしひしと伝わるディスカッションとなった。
サッカーにおいて、ジュニア世代に必要な要素の中で、
スキルはもちろん、今西和男氏が掲げた柱は
“聴く力”
「相手の目を見て、相手の話の内容を理解しようとする子は伸びます」
そして、自分の考えを自分の言葉で“伝える力”
聴き心地のよい語尾を使いながらも、核心をもって言い切った今西氏。
サッカーから離れ、会社人・社会人として試行錯誤した十数年間が、
同氏にとって、
また、GMとして育て上げたサンフレッチェ広島にとって、
重要な期間であったことが充分に伝わってきた。
大分県サッカー協会と大分トリニータ共同開催の講演会
今西和男氏の「共に育つ~今、大分にレガシーを伝える~」に参加した昨夜は、
私が今後どのようにサッカーに携わらせていただけるのかを考える
素晴らしい機会となった。
Jクラブの地域貢献・交流の大切さ、
クラブ繁栄の手っ取り早い魔法を望むより
選手の自立心を育み、社会人としての降るまい、コミュニケーション能力を
育むことの重要さ
そんなことを改めて、確認させられた気がした。
これからの日本のサッカーが最も育てなくてはいけないのは
“勝つ心”だと、今西氏。
勝つ心を支える心を育むことが、ジュニア世代の指導者の課題だと思う。
激しいあたりや、プロの試合を稚拙にまねた、ファウルのとり方など
そんなスキルを教える前に、育まなければならないことが、
たくさんあると、心の中で確認した。
2016年10月13日
パフォーマンス向上のための動作改善エクササイズ体験会
11月23日水曜日 14時~16時
パーソナルコンディショニングハウス ここから屋 で
パフォーマンス向上のための
「動作改善エクササイズ体験会」開催します。
練習中にこんなことを感じている選手は
解決の糸口が見つかること間違いなしです。
「もっと、こう、腕を引いてごらん」といわれても
「意識してやっているのに、ちゃんと腕を引けない」
「もっと!こうやって!踏み込んで、蹴ってみろ!!!!」
と、身振り手振りで力説されても
「踏み込んでるつもりなんだけどなぁ~」
「そう、一歩目、一歩目なんだよな~そこ速くできない?」
と、簡単に言われても
「それができたら苦労はしない」
みなさんの“できない理由”を見つけます!
そして、その理由を解決して
“できる”ようにする方法をお伝えします。
定員は限定6名様。親子での参加可。
参加費はお一人1500円。
お問い合わせは、
ここから屋 080-5207-77897 三橋まで。