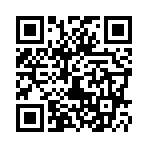2020年08月24日
スポーツとともに送る人生を考える①
スポーツ進学の選択肢が豊富になってきた昨今、
進路選択の低年齢化も進んで来ています。
スポーツをするのは本人ですが、
その低年齢化によって、ますます必要になってくるのは、
選択肢それぞれの育成内容を吟味することと、
保護者の知識向上。
かつて新聞で連載していた記事時の内容は、
16年の歳月を経て、普通の小・中学生、高校生に
当てはまるないようになってきたと感じます。
この機会に、ぜひ、保護者の皆さんに読んでみて、
考えてほしいと思い、長い文章ですが、
再編纂して、掲載してみます。
三橋由里のウエルネストーク
「ポスト・アスリート」(競技引退後の人生)に関する研究は
古くは1950年代、プロボクサーを対象にアメリカで行われといた。
彼らの場合、引退後まず収入が激減する。衝撃の激しいインパクトスポーツであることから、思考能力に障害をきたし、セカンドキャリアの選択に支障をきたすこともある。
何よりも、周囲の人間からの“もてはやし”がぱったりとなくなる事例が多く、心のケアや就職のサポートの必要性が指摘されている。
そこから50年。日本のJリーグでも引退後の選手の心理や状況は、同様な軌跡をたどることがあるようだ。
「社会の通常理念を十分理解しないままプロの世界に入った若手選手ほど、移籍やセカンドキャリアへの移行が困難な場合が多いですね」というのは元日本代表選手で、現在大分トリニータの職員である前川和也氏。Jリーグ選手会の支部長を務めた経験もある。
例えば、高校卒業後すぐにJリーガーとして年俸制で高額を所得する。5年以内くらいで戦力外通告を受け、移籍先もなかったとする。コーチやサラリーマンの月給制にそれまでとのギャップを感じる。会社組織内の礼儀や通常理念にも戸惑いを感じる。過去の自分と現在の自分の違いに馴染めないことにも気づく。
一方で、「ピッチ以外でもいろいろな経験をし、人とのつながりを広げることができた選手は、自分自身で徐々に引退後の準備ができている」。前川氏自身は、イングランドでプレーしたころに触れたサッカー選手に対する処遇や制度、海外遠征などの経験が役立ったそうだ。
本年度、活動3年目を迎えた同リーグのCSC(キャリア・サポート・センター)は、OBに対するケアやサポートと同時に、現役の選手に向けた教育的プログラムにも力を注いでいる。
前川氏はこう語る「プロ選手の指導者免許取得枠を広げるなどの制度も整えてもらいたい」。
苦境に耐え、それを乗り越えて最後に大輪の花を咲かせることが美徳とされる精神文化が根強い日本。それゆえ、有終の美を飾れなかったアスリートに襲いかかる心理的ダメージは計り知れない。加えて、セカンドキャリアにもある種の成功を求めてしまう。
びわこスポーツ成蹊大学の豊田則成氏(スポーツ心理学博士)は、「競技の経験は人格形成に深くかかわってしまう。競技を通して体験し、習得したことが、その人の根底に脈々と生き続ける。この現象は、スポーツへのどのような参加レベルでも共通。だからこそ、ポスト・アスリートに関する研究やサポートシステムの整備が重要だと思うのです」。
進路選択の低年齢化も進んで来ています。
スポーツをするのは本人ですが、
その低年齢化によって、ますます必要になってくるのは、
選択肢それぞれの育成内容を吟味することと、
保護者の知識向上。
かつて新聞で連載していた記事時の内容は、
16年の歳月を経て、普通の小・中学生、高校生に
当てはまるないようになってきたと感じます。
この機会に、ぜひ、保護者の皆さんに読んでみて、
考えてほしいと思い、長い文章ですが、
再編纂して、掲載してみます。
三橋由里のウエルネストーク
「ポスト・アスリート」(競技引退後の人生)に関する研究は
古くは1950年代、プロボクサーを対象にアメリカで行われといた。
彼らの場合、引退後まず収入が激減する。衝撃の激しいインパクトスポーツであることから、思考能力に障害をきたし、セカンドキャリアの選択に支障をきたすこともある。
何よりも、周囲の人間からの“もてはやし”がぱったりとなくなる事例が多く、心のケアや就職のサポートの必要性が指摘されている。
そこから50年。日本のJリーグでも引退後の選手の心理や状況は、同様な軌跡をたどることがあるようだ。
「社会の通常理念を十分理解しないままプロの世界に入った若手選手ほど、移籍やセカンドキャリアへの移行が困難な場合が多いですね」というのは元日本代表選手で、現在大分トリニータの職員である前川和也氏。Jリーグ選手会の支部長を務めた経験もある。
例えば、高校卒業後すぐにJリーガーとして年俸制で高額を所得する。5年以内くらいで戦力外通告を受け、移籍先もなかったとする。コーチやサラリーマンの月給制にそれまでとのギャップを感じる。会社組織内の礼儀や通常理念にも戸惑いを感じる。過去の自分と現在の自分の違いに馴染めないことにも気づく。
一方で、「ピッチ以外でもいろいろな経験をし、人とのつながりを広げることができた選手は、自分自身で徐々に引退後の準備ができている」。前川氏自身は、イングランドでプレーしたころに触れたサッカー選手に対する処遇や制度、海外遠征などの経験が役立ったそうだ。
本年度、活動3年目を迎えた同リーグのCSC(キャリア・サポート・センター)は、OBに対するケアやサポートと同時に、現役の選手に向けた教育的プログラムにも力を注いでいる。
前川氏はこう語る「プロ選手の指導者免許取得枠を広げるなどの制度も整えてもらいたい」。
苦境に耐え、それを乗り越えて最後に大輪の花を咲かせることが美徳とされる精神文化が根強い日本。それゆえ、有終の美を飾れなかったアスリートに襲いかかる心理的ダメージは計り知れない。加えて、セカンドキャリアにもある種の成功を求めてしまう。
びわこスポーツ成蹊大学の豊田則成氏(スポーツ心理学博士)は、「競技の経験は人格形成に深くかかわってしまう。競技を通して体験し、習得したことが、その人の根底に脈々と生き続ける。この現象は、スポーツへのどのような参加レベルでも共通。だからこそ、ポスト・アスリートに関する研究やサポートシステムの整備が重要だと思うのです」。
Posted by さらら at 12:19│Comments(0)